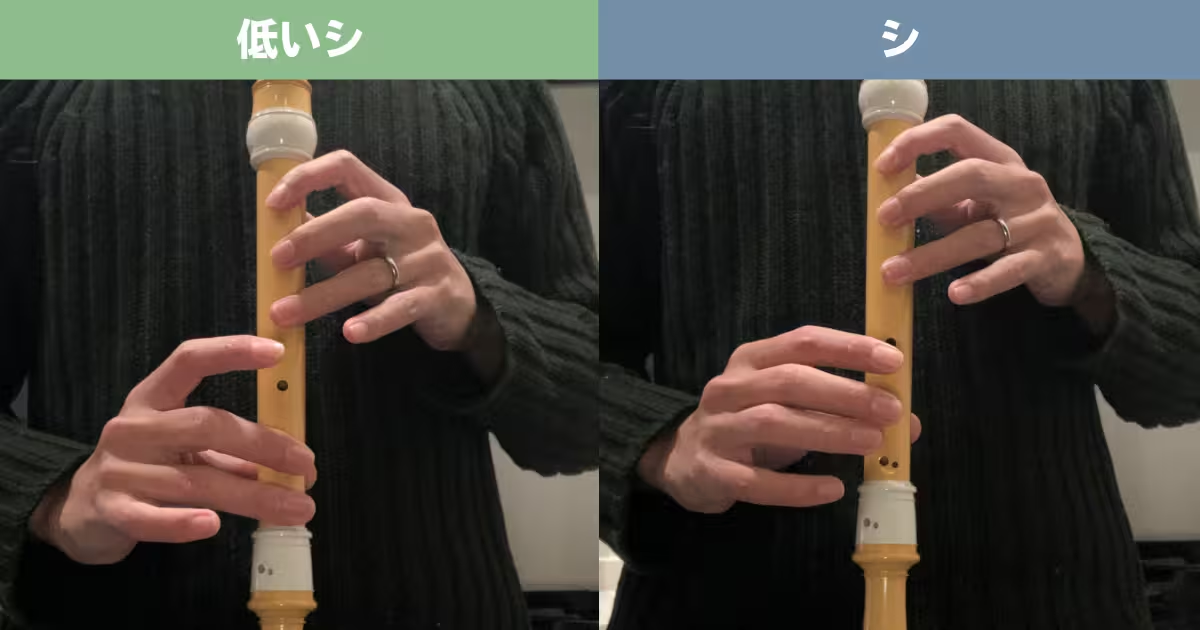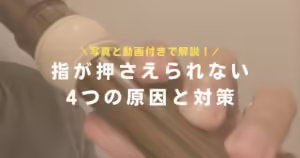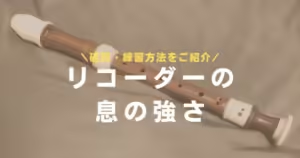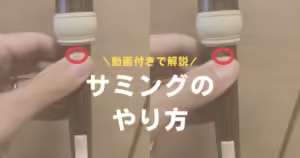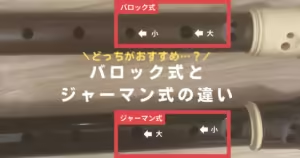「アルトリコーダーのシの音ってどうやって出すの?」
アルトリコーダーのシの出し方は、以下の画像の通りです。

左手の全ての指、右手の中指・薬指を押さえねばならないので、けっこう難しいですね。
ちなみに、サミングのシ(高いシ)は、以下の通りです。
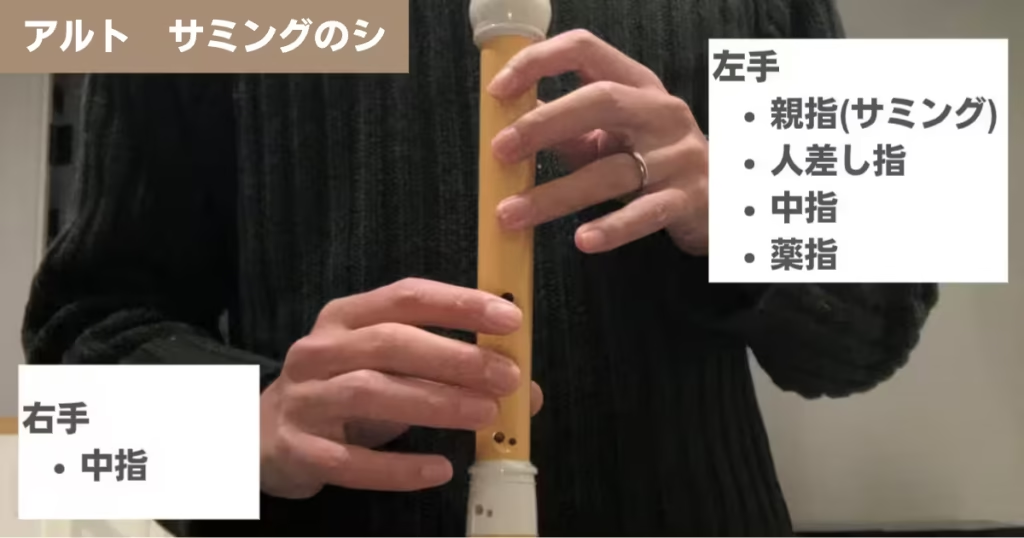
右手が中指だけになって簡単になりますが、左手は親指はサミングなので、苦手な方もおられるかもしれませんね。
アルトリコーダーのシは、私も中学生のときに戸惑った記憶がありますので、詳しくご説明します。
シの指使い
アルトリコーダーのシの指づかいは、音域によって異なります。
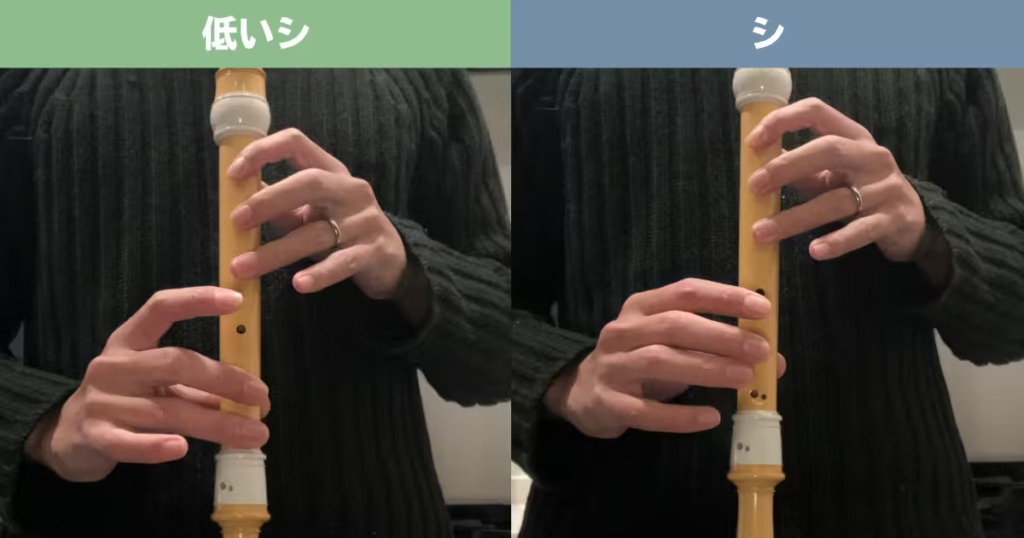
それぞれご説明しますね。
低いシの指使い
低いシの指づかいは、以下の画像の通りです。

- 左手:親指、人差し指、中指、薬指
- 右手:中指、薬指
押さえる指が多くて大変ですね。
高いシの指使い
高いシの指使いは、以下の画像の通りです。
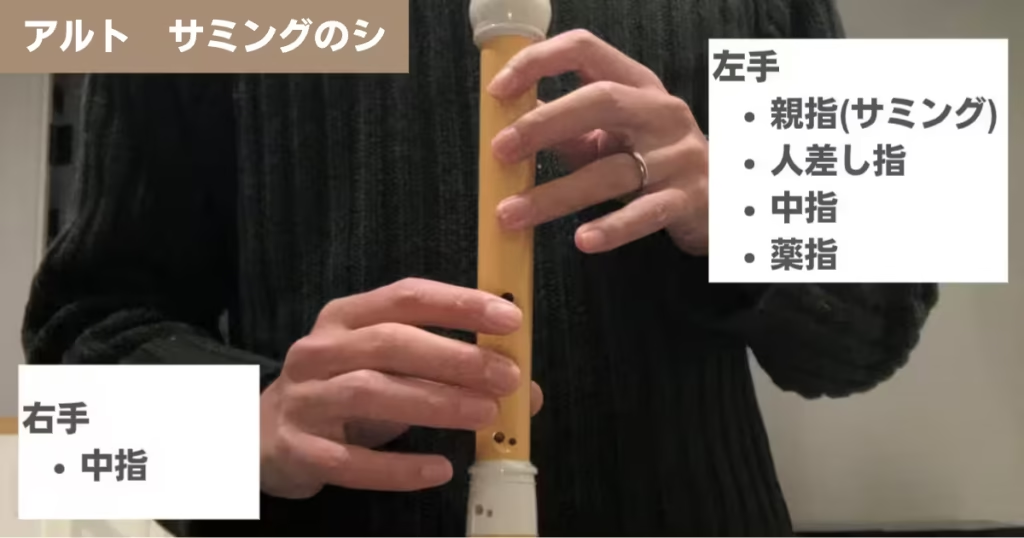
- 左手:親指(サミング)、人差し指、中指、薬指
- 右手:中指
サミングとは、左手親指をずらして、サムホールに隙間をつくることです。
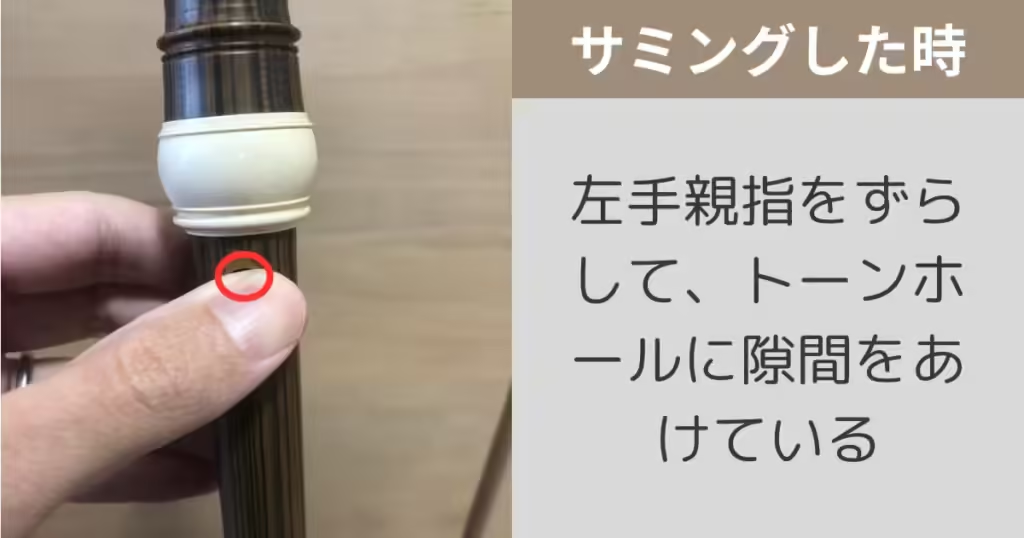
シの練習方法
アルトリコーダーのシは、次のステップで練習するのがおすすめです。
- まずは低いシを練習
- 高いシを練習
まずは低いシを出せるようになれば、サミングするだけで高いシを出せますよ。
まずは低いシを練習
まずは低いシを練習しましょう。

でも、いきなり全ての指を正確に塞ぐのは難しいですよね。
ですので、まずは「真ん中のミの音」を出して、「ミーレードーシー」と順に出していくのがおすすめですよ。
- トーンホールを正確に塞ぐ
- 息が強くなりすぎないように
トーンホールを正確に塞げていなかったり、息が強すぎると音が裏返ってしまうため、気をつけましょう。
機械的に指の練習をするのは飽きてしまうので、サミングなしで吹ける曲を吹いて練習するのがおすすめですよ。
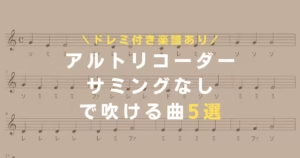
高いシを練習
低いシを出せたら、高いシにも挑戦してみましょう。
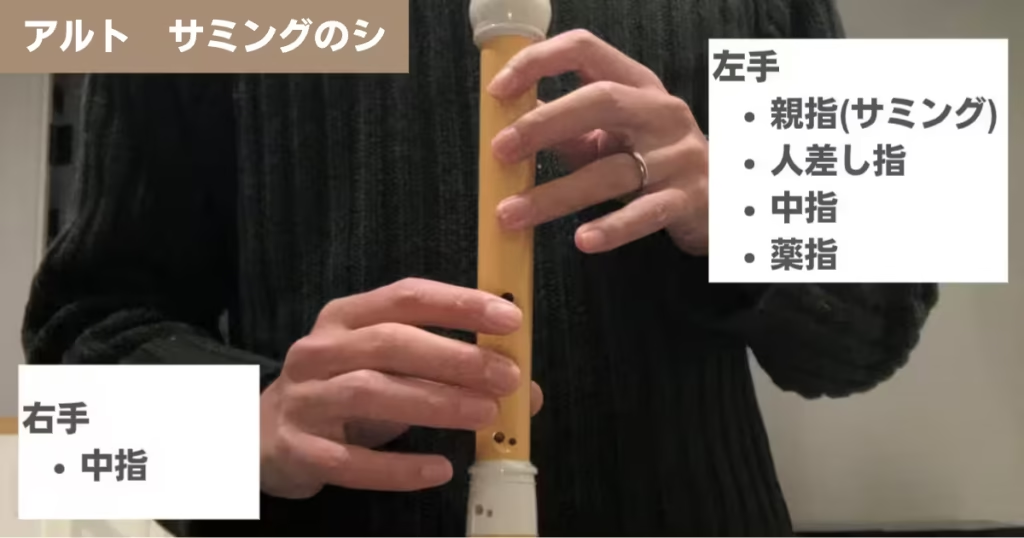
低いシを出したままサミングして、右手薬指を抑えるのをやめれば、高いシが出ますよ。
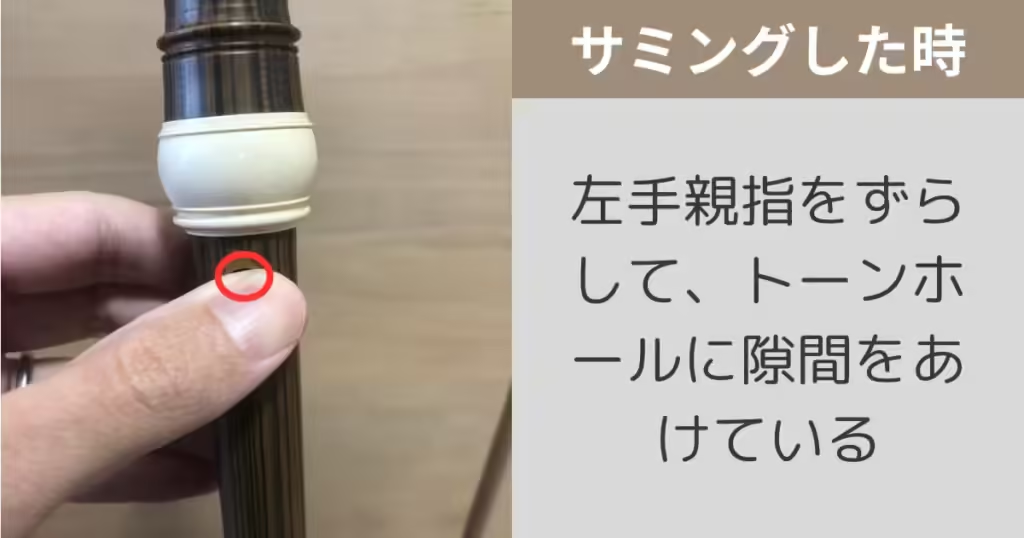
- サミングの隙間を適切に
- トーンホールを正確に塞ぐ
- 息が強くなりすぎないように
サミングの隙間が大きすぎ(小さすぎ)ると出にくくなりますので、注意しましょう。
繰り返し練習して、ちょうど出しやすい隙間を探ってみてくださいね。
ソプラノリコーダーのファと指づかいが違うのはなぜ?
ソプラノリコーダーのファと指づかいが違うのはなぜ?
私は中学生のとき思いましたので、解説しますね。
- 楽器の調の違い
- 運指方式の違い
楽器の調の違い
ソプラノリコーダーとアルトリコーダーでは、楽器の調が異なります。
調とは、楽器の基本となる音のことで、調が変わると同じ指づかいで出せる音階が変わるんです。
- ソプラノリコーダー
- 調:C調
- 音階:ドレミファソラシド
- アルトリコーダー
- 調:F調
- 音階:ファソラシドレミファ
ソプラノリコーダーとアルトリコーダーでは、同じ指づかいで出せる音が違うんです。
アルトリコーダーのドの運指は、ソプラノリコーダーのソと同じですね。
したがって、アルトリコーダーでドレミファソラシドと吹くためには、ソプラノリコーダーのソラシドレミファ♯ソと同じ運指をせねばなりません。
ファに♯が付くんです。
アルトリコーダーのシは、ソプラノリコーダーのファ♯と同じ指づかい。
だから、アルトリコーダーのシとソプラノリコーダーのファでは指づかいが違うんですね。
運指方式の違い
ソプラノリコーダーを熱心に練習して、ファ♯の指づかいを知っている方は「いやいや。ソプラノのファ♯とアルトのシも指づかい違うんだけど…」と思われるかもしれません。
その違いは、運指方式からくる違いです。
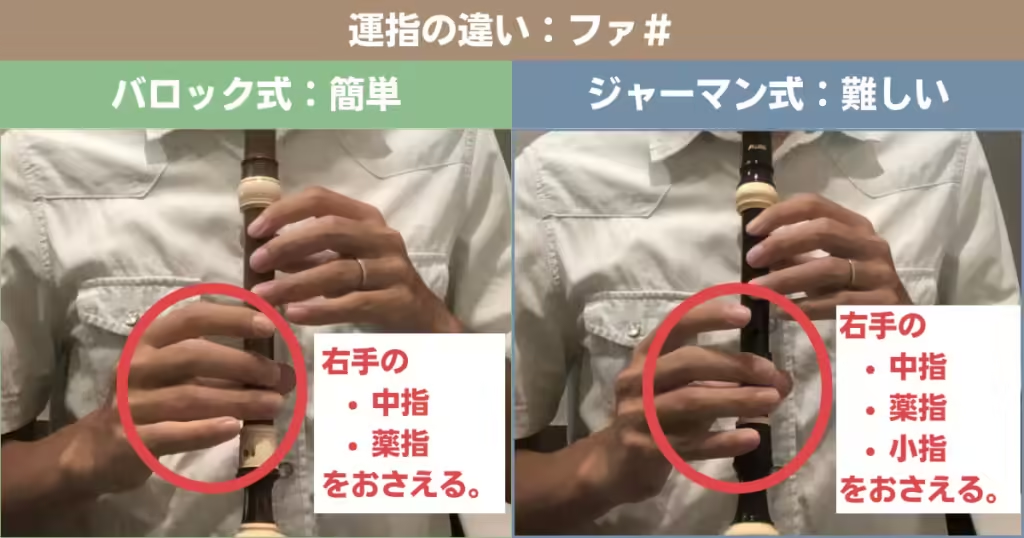
小学校のソプラノリコーダーはジャーマン式なことが多く、バロック式のアルトリコーダーとは、ファ♯の運指が違うんです。
バロック式のソプラノリコーダーのファ♯は、アルトリコーダーのシと同じ指になりますよ。
ちなみに、趣味で演奏する場合は、バロック式リコーダーの方がおすすめです。
♭や♯が付く曲を簡単に演奏できるため、私もバロック式を使っていますよ。
まとめ
アルトリコーダーのシの指づかいについてご説明しました。
最初は難しいかもしれませんが、慣れればそれほど難しくありませんので、繰り返し練習して覚えましょう。