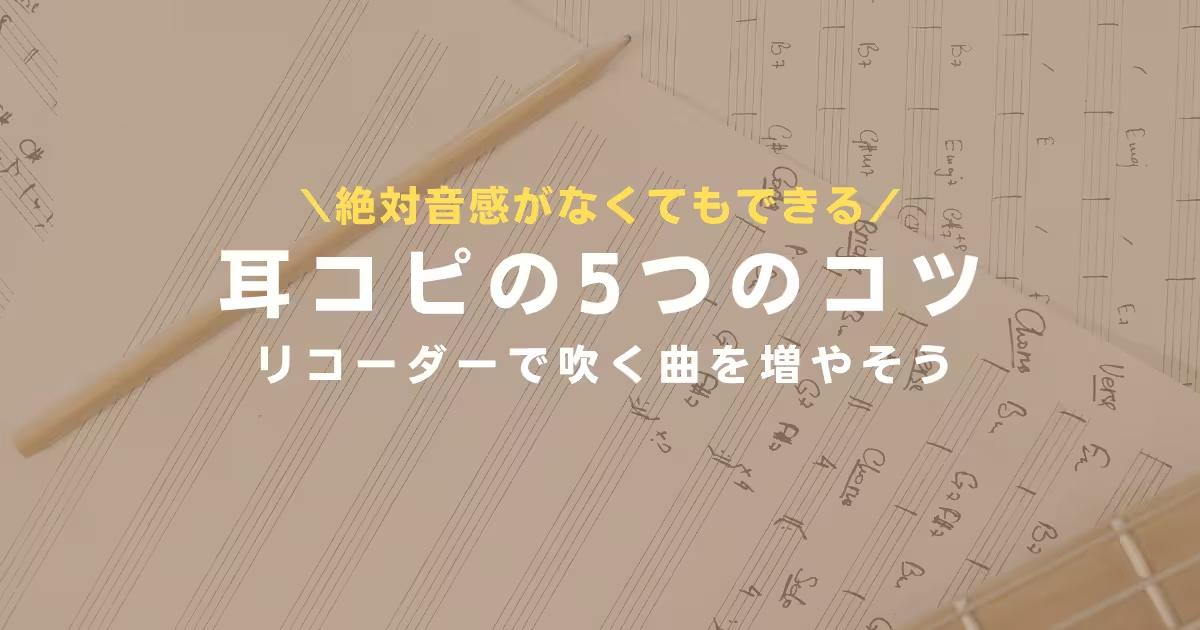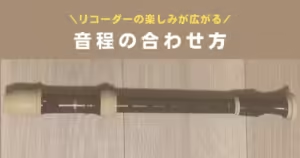「リコーダーは好きだけど、同じ曲ばっかりじゃ飽きるな…。でも楽譜を買うとお金がかかるしな…」
そのような方は耳コピに挑戦するのがおすすめです。
- 耳コピのやり方
- “絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ
- 耳コピのメリット・デメリット
- 耳コピの便利ツール
リコーダーは楽しいですが、それでもいつも同じ曲ばかりでは飽きてしまいますよね。
かといって楽譜を買うのは面倒だし、お金もかかる…
と言うわけで、私は耳コピによってレパートリーを増やしています!
普段遊びで吹いている曲のほとんどは耳コピですし、演奏会で使う曲(チャールダーシュ)も耳コピしましたよ。
耳コピは絶対音感がなくてもできるので、ぜひ挑戦してみてくださいね(私も絶対音感ありません)。
耳コピのやり方
耳コピは次の2ステップで行います。
- 耳コピしたい音楽をよく聞く
- リコーダーで吹いてみる
曲をよく聞いて、それをリコーダーで再現する。これだけです。。。
これだけなんですが、われわれ絶対音感の無い人間には難しいんですよね。
ということで、私が実践している耳コピのコツをご紹介します。
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツをご紹介します。
- 自分の声で歌ってみる
- 1つでもいいから音を探り当てる
- 当てた音から曲の調を考える
- 曲の調から残りの音を予想していく
- 楽器で演奏している動画の指を見る
自分の感覚や楽典・楽器の知識などを総動員して、耳コピをしていく感じですね。
自分の声で歌ってみる
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ1つ目は、曲を聞きながら自分の声で歌ってみることです。
- リズムを体感できる
- 音程をつかめる
- 音と音の間隔を体感で測れる
リズムや音程などを体感することで、ただ耳で聞くよりも、曲の構造をより深く正確につかめるようになりますよ。
1つでもいいから音を探り当てる
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ2つ目は、1つでもいいから音を探り当てることです。
いきなり全ての音を当てるのは難しいですよね。
でも1つの音なら、何度も聞いたり歌ったりしていれば探り当てられることもあります。
- 直感で当てる
- (動画があれば)指づかいから当てる
- 全ての音(12パターン)を総当たりで検証して当てる
最悪、全ての音(12パターン)を総当たりで検証すれば、1つの音なら分かりますよね。
かなり泥臭い方法ですが、この1つの音が大きな一歩となりますよ。
当てた音から曲の調を考える
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ3つ目は、当てた音から曲の調を考えることです。
曲の調とは、ざっくり言うと「その曲の基本となる音階」です。
例えば、ハ長調の曲だったら「ドレミファソラシド」を中心にして構成される曲、という感じですね。
曲の調が分かると、“次に来そうな音”が予想できるので、耳コピが断然やりやすくなりますよ。
曲の調は、次の2つから予想しています。
- 曲の響き
- 探り当てた複数の音
曲の調は、間違っていても大丈夫です!
もし間違っていたら、耳コピを進めていく途中で修正していきましょう。
曲の調から残りの音を予想していく
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ4つ目は、曲の調から残りの音を予想していくことです。
曲の調が分かると、残りの音で使われる可能性が高い音が分かるので、それを元に残りの音を検証していきましょう。
私の場合は、次の2つの要素から音を検証しています。
- 曲の調の音かどうか
- 自然に曲に馴染んでる音
→曲の調の音 - アクセントになっている音
→曲の調でない音
- 自然に曲に馴染んでる音
- 音と音の間隔はどのくらいか
かなり感覚的な部分もありますが、これらを考えながら1つ1つの音を特定していく感じですね。
難しいときは、曲を自分の声で歌ってみると分かりやすくなりますよ。
楽器で演奏している動画の指を見る
“絶対音感がなくてもできる”耳コピの5つのコツ5つ目は、楽器で演奏している動画の指を見ることです。
楽器は出す音によって、指使いが違いますよね。
それを利用して、指を見て音を予想することも可能ですよ。
私は、リコーダー・金管楽器・クラリネット・ピアノであれば指を見れば音を予想できるので、どうしても音が分からない時はYoutubeなどの動画で指を見ています。
もはや“耳”コピではないので、これなら耳の良さは関係ありませんね(笑)。
ただ、動画の指の動きが速すぎたり、あまり指が映ってなかったりして分からないことも多いので、ここまでにご紹介した耳コピの方法を基本にしましょう。
耳コピのメリット・デメリット
耳コピのメリットとデメリットは次の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 耳がよくなる 楽譜代がかからない 演奏できる曲が増えて楽しい | 他の人との共有ができない 時間がかかる 音を間違えてしまうこともある |
耳がよくなるのと楽しく演奏できることのメリットが大きすぎますね。
耳が良くなると、ソロでもアンサンブルでもよい演奏ができるようになるりますよ。
多少のデメリットはありますが、耳コピを練習しない理由にはならないと思いますので、耳コピの練習をしてみてくださいね。
耳コピの便利ツール
耳コピがしやすくなる便利ツールをご紹介します。
- ピアノ
- 耳コピアプリ
耳コピの音を確かめるのは、リコーダーよりもピアノの方がやり易いです。
リコーダーよりもピアノの方が視覚的に音が分かりますし、音程も確実なので、耳コピがしやすくなりますよ。
また、最近では耳コピアプリもあるようです。
- ゆっくり再生したり
- ループ再生したり
- 自動で採譜したり
耳コピが便利になる機能が搭載されているようで、耳コピがはかどること間違いなしですね。
耳コピに便利なツールを使いこなして、効率よく耳コピをしていきましょう。
まとめ
絶対音感が無くてもできる耳コピの方法について、ご説明しました。
- 自分の声で歌ってみる
- 1つでもいいから音を探り当てる
- 当てた音から曲の調を考える
- 曲の調から残りの音を予想していく
- 楽器で演奏している動画の指を見る
耳コピの練習をすると、吹ける曲が増えて楽しくなるだけでなく、耳が良くなってリコーダーが上手になりますので、ぜひ練習してみてくださいね。
「でもやっぱり耳コピは難しい~」という場合は、プロに依頼してみる方法もありますよ。
ココナラ(プロが集まる日本最大級のスキルマーケット)では、1曲数千円程度の値段で耳コピをしてもらえます。
- 楽譜がないけどどうしても演奏したい曲がある
- 憧れの演奏家のアドリブを再現したい
- 耳コピを頑張ったけどできなかった
- 耳コピしたいけど時間がない
ココナラの会員登録は無料でできますので、依頼したい方は試してみてくださいね。